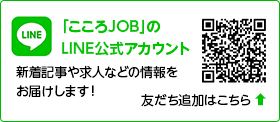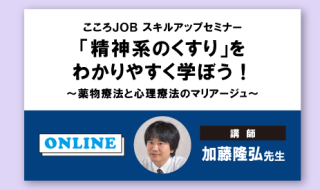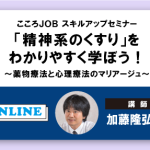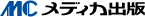誤解の多い認知行動療法を正しく理解し、ユーザーを支えてほしい ~認知療法・認知行動療法の第一人者にきく②~
- 2019-10-10
- 公認心理師に期待すること, 心理職で働く, 病院
認知行動療法の第一人者として知られる、一般社団法人認知行動療法研修開発センター理事長・ストレスマネジメントネットワーク代表の大野裕先生。認知行動療法については、誤解されている部分があるという。誤解とは何か、心理士は認知行動療法にどう関われば良いかなどについて伺った。
――大野先生は認知行動療法の実践と普及に、長く取り組んで来られたと思います。心理士の国家資格として公認心理師が創設され、その教育課程に認知行動療法の学習が位置づけられましたが、これをどのようにとらえていますか。
大野 良い部分と悪い部分があるのではないかと考えています。良い部分は、もちろん多くの人に認知行動療法を学んでもらえることです。しかし、今、認知行動療法には誤解されている部分があります。正しく学習してもらえればいいのですが、中途半端な理解で誤解が拡散されてしまうリスクも感じています。それが悪い部分です。
例えば、「職場の同僚が食事に行くのに、自分だけが誘われなかった。自分は嫌われているのだ」と落ち込んでいる方に、「あなたの仕事が忙しいから、みんな気を遣ってくれたのだと、気持ちを切り替えたらどうですか」と言う。そして、「そのときの気持ち、頭の中のイメージ、行動、体の反応を書き出してみましょう」と指導したりする方がいます。
しかし、そもそも声をかけてもらえないとすれば、好かれていない可能性が否定できません。そのときに「仕事が忙しいから気を遣ってくれた」などと考えると、それこそ「空気を読めない人だ」と思われてしまいかねません。
この落ち込んでいる方にとっての問題は、嫌われているかどうかではなく、「嫌われている自分はダメだ」と考えて、それ以上行動をしなくなってしまうことです。この方は、本当は同僚と一緒に食事をしたいわけです。では、それがなぜ実現されていないのか。そこで「ダメだ」と諦めるのではなく、どうすればいいかを考えていく。何をすれば少しでも状況を変えていける可能性があるかを一緒に考えるのが、認知行動療法の基本的なスタンスです。
それが今、テストで答えを書くかのように形式的になりすぎ、それが広まっていると感じています。公認心理師の教育課程に入ることで、みなに正しいスタンスを身につけてもらえることを願っています。
――認知行動療法の面接技法は、習得が難しいのでしょうか。
大野 そうではありませんが、面接技量には心理士によるバラツキがあるのが実態です。このバラツキをなくすために認知行動療法の面接にコンピュータを活用できないかと考え、私が監修している「こころのスキルアップトレーニング」を使って行うインターネット支援型認知行動療法の効果検証を続けてきました。
それと並行してユーザーの気持ちに寄り添いながら声かけをする、AIを使ったチャットボットも制作しています。たとえば、「どうしたらよいと思いますか」「少し考え方を振り返りましょうか」「そのとき、どんなことを考えていましたか」など、ユーザーの思考過程に対応して、ユーザーが自分で考えられるような声かけの言葉を発するのです。まもなくベータ版をリリースする予定です。
なぜロボットかと言えば、人間が相対するよりユーザーのことを傷つけにくいからです。人は相手が人間だと、「これくらいわかってほしい」と期待してしまいます。しかし、ロボットなら過度な期待をせずにすみます。それに、認知行動療法でスキルとして身につけたい行動パターンは、人間ではなくロボットを相手に練習しても十分だからです。
――そのとき、心理士はロボットとどのように協働すればよいのでしょうか。
大野 基本的なスキルの修得はロボットやインターネットにまかせて、もっと人間的な交流に力を注いでほしいと思っています。一緒に喜んだり悲しんだりしながら、うまくユーザーの背中を押していく。ロボットとのやりとりのあと、ここで困った、というような相談に応じるなど、取り組み全体を見渡して、ユーザーを人間的に支えていく役割を担ってもらえればと思います。
――認知行動療法は、いま、精神科領域だけでなく、身体疾患の領域でも広く活用されていると聞いています。
大野 例えば、慢性疼痛がある方の場合、痛みがあるからつらくていろいろなことができないと考えがちです。そう考えると、痛みをいっそう大きく感じるようになります。このとき、痛みがあるのは事実です。一方で、その痛みをさらに自分で大きくしている部分があるのです。痛みがあるから外に出られない。痛みがあるから仕事もできない。そんなことを考えていると、「できない自分」がますます意識されますし、そのためにますます気持ちが沈んでいきます。気持ちが沈むと、痛みはさらに大きくなります。
この悪循環を断ち切るために、根源的な痛みと、自分で増幅させている痛みを切り分けて、痛みを抱えながら何ができるのか、何がしたいのかを考えていく。切り分けることによって、痛みではなく、自分のしたい生活を拡充していくために使うのが、認知行動療法です。
今は、生活習慣病や認知症においても、どうすれば自分らしく生きられるのかを考えるために、認知行動療法が使われています。
――認知症では、どのように認知行動療法が使えるのですか。
大野 良い例が、若年性認知症を持つ当事者として活動されている佐藤雅彦さん(*1)の取り組みです。佐藤さんは一人暮らしをしていて、若年性認知症の診断を受けて絶望的な気持ちになりました。これでもう、一人暮らしができなくなるのではないかと考えたそうです。しかし、そこで佐藤さんは、一人暮らしをしていく上で何が問題かを考えました。そして、問題は記憶を維持できないことであり、これに対処するには自分の頭以外の記憶装置を持てばいいと考えたわけです。
最初は、メモを書いていました。しかし、メモは散逸してしまう。そこで、知人に設定してもらって、タブレット端末を使うようにした。佐藤さんは、この ”外部記憶装置“ を使うことで、「記憶を維持できない」という問題を解決できました。これで佐藤さんは、認知症の診断を受けた後も、一人暮らしを続けるという選択ができたのです(現在は、ケアハウスに居住)。
(*1)佐藤雅彦さん……2005年に51歳で若年性認知症の診断を受ける。本名を明かして認知症当事者としての情報発信をした先駆的存在。現在も、講演活動やウェブサイトで、認知症と共にどう生きるかについて、広く伝えている。著書に「認知症になった私が伝えたいこと」など。
――問題を切り分けてそこに焦点を当て、その対応方法を考えていくのに、認知行動療法は有効だということですね。
大野 別の例を出すと、私がアメリカに行っていた1980年代後半、大きな問題となったエイズについても、同じようなことがいえます。当時、エイズの発症の原因はまだはっきりせず、HIVが関係しているのではないかといわれていた頃です。治療法もまだわからず、発症したら死を待つしかないといわれていました。
それで、HIVポジティブの診断を受けると絶望的になり、自分はエイズになって、もう死んでしまう、もう何もかもどうでもいいと考える人が多かった。そして、不適切な行為を繰り返して、ウイルスをまき散らす人が後を絶たなかったのです。
しかし実は、HIVポジティブとわかってからエイズを発症するまでには何年もかかります。そしてエイズを発症してから亡くなるまでにも、やはり何年もかかるのです。少し冷静になって考えると、HIVポジティブと診断されたからといって、明日にも死んでしまうわけではないのです。そこで、HIVポジティブの診断を受けても絶望に打ちひしがれるのではなく、もっときちんと現実を見て、何をすればいいかを考えようと、認知行動療法を使った研究が行われるようになったのです。
今は、がんもまた、慢性疾患のような扱いになってきています。認知症もエイズもがんも、その病気を持ちながらどう生きていくのが大事になっているのです。
――そこで心理士はどんなことができるでしょうか。
大野 病気の治療を行うのは医師ですが、「病気を持ちながらどう生きていくか」という心理的な部分は、心理士の専門領域です。アメリカで、認知行動療法を使ったエイズの研究を行っていたのは、心理士でした。もちろん、研究だけでなく、患者、ユーザーにとっては、心理士が関わることで、とても役に立つサービスを提供できると思っています。
*大野 裕先生が、医師との協働など、心理士に対する思いと期待などを語ったもう一つの記事はこちら
(インタビュー・文:介護福祉ライター/公認心理師・臨床心理士・社会福祉士 宮下公美子)